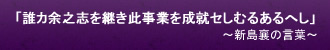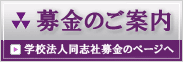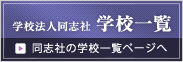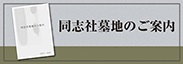�͂��߂�
�@�{���ȉ�ł́A���q�����ɂ�������̌����w�Z�}���فE�i�����@�̖����ɂ��Č��y���A����̉ۑ�ɂ��čl���Ă��������B
�w�Z�}���قƏ�p�\��
(1)���Ƃ�
�@�|�����Ȋw�ȁw����̏�Ɋւ������x(2010�N10��)��4�́|
�@�E�������k�̏�p�\�͂̈琬��}�����
�@�E���̖ڕW
�@A.��p�̎��H�́@B.���̉Ȋw�I�ȗ����@C.���Љ�ɎQ�悷��ԓx
�@�|�w�}���ُ��w�p���T�x��4�Ł|
�@�u��p�\�́v�̈琬���傽��˂炢�Ƃ�������
�@
(2)��p�\�͂Ƃ�
�|�w���{��S�ȑS���i�j�b�|�j�J�j�x�|
��p�\�͂Ƃ́A�u�������i��ړI�Ɋ�Â��đI�����A���p���邽�߂ɕK�v�Ȍl�̊�b�I�����v�ł���A�u�L�`�ɏ�e���V�[�v�Ƃ��āA�u�c��ȏ����g�����Ȃ��A����̖ړI���Ȃ����邽�߂ɏd�v������Ă������́v�ƒ�`����Ă���B
����p�\�́i����e���V�[�j��2020�N�x�̐V������w�������x�ŁA�]���̋��Ȃ̖����z���ďo�肳�������������߂ɕK�v�s���Ȕ\�͂ł���ƍl������B
�@
(3)�w�K�w���v�̂Ɗw�Z�}����
�@�w�Z�}���ق́A�}���E�G���E�V���EWEB�ȂǑ��l�ȃ��f�B�A���������Ƃ�O��ɁA�l�X�ȏ�̒�������𐳂����]�����A�g�p����\�͂��琬���Ă�������������B��p�\�͂̏d�v���͊w�K�w���v�̂ɂ��L�ڂ���Ă���A���Ɋw�K�̊�ՂƂȂ鎑���\�́E����\�͂ƕ���ŏ�p�\�́A��蔭���E�����\�͂̏d�v�����L����Ă���B�܂��A���ȓ��̉��f�I�Ȋw�K���d�����Ă���A���ȓ����f�I�Ȋw�K�͊w�Z�}���ق̍ł����ӂƂ��镔���ł���ƍl����B����ɁA�w�Z�}���ق́A�e���Ȃɂ�����K�v�ȏ��𑵂��Ă���A���ȊԂ̊w�т���������ƁA�S���Ȃ����f���Č����邱�Ƃ���A�S���Ȃ̊w�т���т��Č���Ƃ�������������ƍl����B
�@
(4)�w�Z�}���ق�3�̋@�\
�@�u�Ǐ��Z���^�[�v�Ƃ��Ă̋@�\
���S�ȋ��{���琬���A���t�̗͂�L���Ȑl�Ԑ�����Ă�@�\
�A�u�w�K�Z���^�[�v�Ƃ��Ă̋@�\
�w�Z�̋���ے��̓W�J�Ɋ�^���A���⎑���������Ƃ��ėp���Ċw�т�S���@�\
�B�u���Z���^�[�v�Ƃ��Ă̋@�\
���ȉ��f�I�ȏ�p�\�͂̈琬�ɂ�����@�\
�ˍ���͓��ɇB�u���Z���^�[�v�Ƃ��Ă̋@�\�ɂ��Č��y����
�T���̃v���Z�X
(1)�ėp�I�Ȕ\�͂̈琬
�@�w�Z�}���ق́u���Z���^�[�v�@�\�Ƃ��ẮA���k�E���E���̏��j�[�Y�ւ̑Ή��A��p�\�͂̈琬����������B�ȑO�̐}���قł́A�}���ق̗��p�w���Ƃ��āA�u���}���ق̗L���Ȏg�����v���w�����Ă����B�������A���ꂾ���ł͔ėp�����Ȃ��A�������ʂŊ��p�ł���\�͂���Ă�K�v������Ƃ��āA���p�w���̉�������Łu�T���̃v���Z�X�v��̌����w�Ԃ��ƂŁA�ۑ�����ɕK�v�ȗ͂��������T���Ċ��p���Ă����͂ȂǁA�u�ėp�I�Ȕ\�́v���琬���Ă����Ƃ��������ɕς�����B
�@
(2)�l�X�ȒT���^�̊w�у��f��
�@�T���^�̊w�тƂ��āA�T���v���Z�X���d�������l�X�ȃ��f��������B�Ⴆ�A�A�����J�́uBig6 Skills�v��J�i�_�́uFocus on Inquiry�v�A���{�ł́A�����Ȋw�Ȃ́u�T���I�Ȋw�K�ɂ����鐶�k�̊w�K�̎p�v�Ƃ������f��������B
�@
�@
�uBig6 Skills�v��6�̃v���Z�X
1.Task Definition�y�ۑ���`����z
2.Information Seeking Strategies�y���T���̎菇���l����z
3.Location and Access�y��̏��݂��m�F�����W����z
4.Information Use�y���𗘗p����z
5.Synthesis�y���ʂ��܂Ƃ߂�z
6.Evaluation�y�]������z
�˂�����6�̃v���Z�X�͈꒼���ɐi�ނ킯�ł͂Ȃ��A�w�K�̒��Ŏ��s������d�˂Ȃ���i�ށB�v���Z�X���ӎ����Ȃ���w�Ԃ��ƂŁA�ߒ������ʂ��͂�g�ɕt����_��������B�T���̃v���Z�X���o�����A����v���Z�X�����͂�{�����Ƃ��A�u����w�Ԋw�K�ҁv�̖ڎw���p�ł���ƍl����B
�@
�@�u�T���I�Ȋw�K�ɂ����鐶�k�̊w�K�̎p�v��4�̃v���Z�X
1.�ۑ�̐ݒ�@2.���̎��W�@3.�����E���́@4.�܂Ƃ߁E�\��
�ˊw�K�w���v�̂ł́A������4�̃v���Z�X�������I�Ȋw�K�̎��ԂŎ��グ���A�T���^�̊w�K�E�����I�Ȋw�т�������Ă������ƂŁA��̓I�Ȋw�т̎�����ڎw���Ƃ����悤�ɐG����Ă���B
�@
(3)�}���E���Z���^�[�����p��������
�@�w�Z�}���ق��v��I�E�p���I�E�i�K�I�Ɋ��p���邱�ƂŁA�T���v���Z�X��̌����A�T�����@��g�ɕt����Ƃ����w�K���d�v�ł���B�i�����@�́A���Ƃ̒���T.T.(Team Teaching)�Ƃ��Ċw�K�w���ɂ�����B�S�����@�Ƒ��k���d�ˁA�ǂ̂悤�Ȏ��Ƃɂ��A�ǂ̂悤�Ȏ������g���ׂ������l���A�T�|�[�g�����Ă�������������B�܂��A�w�Z�}���قƂ��āA�w�N�ԁE���ȊԂ̘A�����̂��锭�W�I�Ȋw�т��v�悵�Ă����Ƃ�������������B�{�Z�ł́A�T���^�̊w�K��ڎw���āA�l�X�Ȏ��ƂŐ}���E���Z���^�[�����p���Ă���B��ɁA�����I�Ȋw�K�E�����I�ȒT���̎��Ԃł́A��r�I�傫�ȃv���W�F�N�g���Ԃɓn���čs���Ă���B��2�A��3�A��3�Ǝ��Ƃ�ݒ肷�邱�ƂŒi�K�I�E�v��I�E�p���I�ɏ�p�X�L�����w�����邱�Ƃ��ł���B
�@
�y�}���E���Z���^�[�����p�������ƌv��z
�E���w2�N���F�����I�Ȋw�K�̎���
�E���w3�N���F�����I�Ȋw�K�̎���
�E���Z3�N���F�����I�ȒT���̎���
�E�e���Ȃ̎���
�y�}���E���Z���^�[�����p�������Ɨ�z
(��)���w3�N���F�����I�Ȋw�K�̎��ԁF�uBig6 Skills�v�ɓ��Ă͂߂��
1�w���F�l������Ɋւ��l����ǂŒ��ׁA�|�X�^�[���쐬����
�˃v���Z�X��4�C5�C6�ɏd�_��u��������
2�w���F����̐l���������グ�A�l���|�[�g���쐬����
�˃v���Z�X��1�C2�C3�C4�C5�ɏd�_��u��������
3�w���F�쐬�������|�[�g����Ɍl���\���s��
�˃v���Z�X��5�C6�ɏd�_��u��������
���Ɨ�̂悤�ɁA��̉ۑ�őS�Ẵv���Z�X�ɏd�_��u���̂ł͂Ȃ��A�i�K�I�ɏd�_��u���v���Z�X���l���čs���Ă���A�����̎��Ƃ͒����ԂŌv��I�ɍs���邩�炱���ł���w���ƂȂ��Ă���B
�@�y�}���كK�C�_���X�z
�{�Z�Ŏ��{���Ă���}���كK�C�_���X�ł́A�₢�̍�����A�e���f�B�A�̓����E���p���@�A���̂܂Ƃߕ��A���쌠�i�Q�l�����̏������A���p�̕��@�j�Ȃǂ�i�K�I�Ɏw�����Ă���B
(4)�e���Ȃ̎��Ƃɂ�����}���E���Z���^�[�̊��p
�@�����I�Ȋw�K�ȊO�ł��A�e���Ȃ̎��ƂŐ}���E���Z���^�[�����p�������Ƃ��s���Ă���B�e���Ȃ��K�v�ɉ����čs�����߁A�Z���Ԃł͂��邪�A�T���̃v���Z�X�̂ǂ��ɏd�_��u�������Ƃɂ���̂���S�������Ƒ��k���Č��肷��B���Ȃ̖ڕW�Ɛ}���ق̖ڕW�ɍ��킹�ĉۑ�̓��e�⏀�����鎑�������肷�邽�߁A�}���E���Z���^�[�Ɗe���Ȃ̒S�����@�̘A�g���d�v�ƂȂ�B
����̉ۑ�
(1)ICT���̐���
�@�P��ICT���𐮂���Ƃ��������ł͂Ȃ��A���𐮂��邤���ŁA�ǂ̂悤�ȏ�炪�ł���̂����l���邱�Ƃ��d�v�ł���B�V���ȋZ�p�E�@������邱�Ƃɂ�郁���b�g��f�����b�g���������A���ꂩ��̐��E���Ă������ň�ނׂ��͂����ʂ��A���̐����ɂ�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
(2)�V���L���O�E�c�[���̊��p
�@�ėp���̂���V���L���O�E�c�[�������ƂŊ��p���邱�Ƃ��d�v�ł���B�ėp���̂���c�[�����g�p���邱�ƂŁA�}���E���Z���^�[�ł̎��Ƃ����ł͂Ȃ��A�������ʂŊ��p�ł���_���I�Ȏv�l�͂���ނ��Ƃ��ł���ƍl����B
(3)�A�N�e�B�u�E���[�j���O�u��̓I�E�Θb�I�Ő[���w�сv�̑��i
�@��̓I�E�Θb�I�Ő[���w�т�ڎw���A�N�e�B�u�E���[�j���O�ł́A���t�����Ƃ̓����R���g���[������Ƃ��������A���t�����k�ƈꏏ�ɂȂ��Ď��s��������Ȃ���A���Ƃ̖ڕW�ւ��ǂ蒅���Ƃ����w�т��d�v�ł���B���k�̎��含�����܂���A���Ƃ̕������̗\���͓���Ȃ�A���Ƃ̏�������ςɂȂ�B�A�N�e�B�u�E���[�j���O��i�߂钆�ŁA�}���فE�i�����@�͌v��I�Ȏw���v����l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�i�����@�Ƃ����A��p�̐��ƂƂ��āA���k�ɂ��ǂ����Ƃ�����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�܂Ƃ�
�@��p�\�͂��琬���邤���ŁA�w�Z�}���ق̊��p���@�͑�R����B�l�X�ȃ��f�B�A�𑵂��A���Ȃ��z�����w�т���邱�Ƃ��ł���̂����݂ł���A�u�w�ѕ����w�ԁv�ꏊ�̒��w�Z�}���ق̖����ł���ƍl����B��p�\�͂̈琬�A���k�Ə����q���˂����Ƃ��Ďi�����@�͏d�v�Ȗ�����S���Ă���B��p�̐��ƂƂ��Ă̑��݈Ӌ`���l���A��������i���Ă��������B