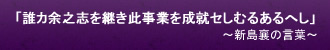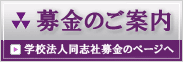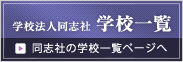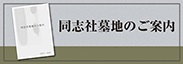総長スピーチ集
2014年度同志社女子高等学校卒業式祝辞(2015年2月20日)
同志社総長 大谷 實
同志社女子高等学校の卒業生の皆さん、ご卒業、誠におめでとうございます。この3年間、辛いことや悲しいことがあったかと思いますが、一生懸命頑張り、高等学校3年間を無事、終了し、今日、晴れて卒業式を迎えられました。皆さんの努力、精進に心から敬意を表したいと思います。本当に、おめでとうございます。また、ご列席のご父母、ご家族の皆さん、心からお嬢様のご卒業をお祝い申し上げます。
さて、卒業生の皆さんは、高校在学時代にNHK大河ドラマ「八重の桜」で、同志社女子高等学校の原点である新島八重の生涯を学ぶ幸運に恵まれました。この経験は、皆さんにとって、おそらく生涯忘れられない貴重なものになるのではないかと思いますが、皆さんは、新島八重の生涯から何を学ばれたでしょうか。
私の学んだことを参考までに紹介しますと、八重の生涯は、大きく4つのステージに分けることができると思いました。初めは、砲術師範つまり鉄砲の扱いを教える山本家で、男勝りの娘として育ち、白虎隊の少年たちに銃の使い方を教え、戊辰戦争では、鶴ヶ城に立てこもり、男の姿で戦った「幕末のジャンヌダルク」として生きた第1ステージ。次は、兄の山本覚馬を頼って京都にたどり着き、新島襄と知り合って洗礼を受けて2度目の結婚をし、新島と一心同体となって同志社の運営・発展に力を尽くす「ハンサム・ウーマンとしての第2ステージ」。さらに、赤十字の社員となり、従軍看護婦を務め、皇族以外で日本で初めて叙勲を受け勲章を受けた「日本のナイチンゲール」として生きた第3のステージ。そして、世間のことに心を奪われることなく、茶道に没頭し、「茶道師範・新島宗竹」として生き、満86歳で神に召された第4ステージ。
こうして振り返ってみますと、新島八重は、当時の女性としては、きわめてユニークな独自の人生を歩んだ方であると言ってよいと思います。問題は、八重はどういうお人柄の女性であったかということです。新島襄研究の第1人者である元・神学部教授の本井先生は、「日本の元気印」「女丈夫(じょじょうぶ)」と申しましたが、私は、八重のお人柄は、自ら治め自ら立つ「自治自立の志」をはっきりと自覚して人生を歩んだ女性であると考えています。先程紹介した八重の生涯の4つのステージすべてに通じるのは、俗事つまり世間のことに振り回されず、自由に、自治自立の志で、自分が正しいと信ずる道を大切にして、強い意志をもって、力強く生きた女性であると思うのです。
女性の社会的進出、女性の生き方や社会的な活躍のあり方が問われている現在、皆さんは、同志社女子高等学校で学んだ女性として、是非、新島八重の生き方を学び、一国の良心として大活躍して欲しい。
結びにあたり、私は、同志社総長として、皆さんお一人お一人が、自治自立の志をもって精進され、素晴らしい女性に成長されることを期待して止みません。
本日は、ご卒業、誠におめでとうございます。